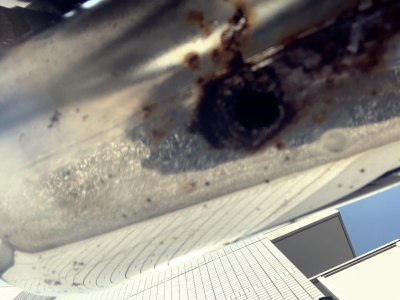私がその浜辺で出会った男は、
見るからに無愛想で暗く、
初め口を聞く気になれなかった。
目の前に広がる冬の海。
水鳥が、来ては返す波に添うように
低い空を舞っていた。
流木が何本も無造作に打ち上げられていた。
今にして思えば、
まるで私のようでもあった。
私は頑固に背を向け続けていたが、
その男は自分の手持ちの酒を
惜しげもなく分けてくれた。
すぐに体が温まった。
私はもっと深く知りたくなり、
その男に名前を訊ねた。
私はその時、自分の名を名乗り忘れた。
しかし彼は気を悪くすることもなく、
それよりも歌を聞いてくれないかと
ニヤリとニヒルに笑って、
古びたギターケースから
ギブソンのJ45を取り出した。
男はしゃがれた、しかし暗闇を携えた声で
本物の歌を歌ってくれた。
それはひとりでその海にたどり着いた私が
必要とする種類の歌だった。
歌はいつだって
人の孤独のためにあった。
その男にとっても同じだろう。
けれど彼は歌う側にいた。
そこがその男の居場所だった。
小さな焚き火が消えかける頃、
やがてライブが終わると
私は愛のこもった拍手を送ったあとで、
君はずっとここにいるのか?
その火が消える前に、
一緒にここを離れよう
そう伝えた。
もっと笑い声がこだまする場所へ行こう
きっと楽しいはずだ、と。
するとその男はこう答えたのです。
僕は大丈夫だよ
僕はここでいいんだ
もし君がまたここに来ることがあったら、
いつでも君のために歌うよ
その場所はここと背中合わせなのさ
だからわざわざ行かなくても、
本当は今もそこにいるのと同じなんだよ
意味を理解できなくてもいい
ただ、君がまたここに迷い込んだ時、
それを押し返すのが俺の仕事なんだ、と。