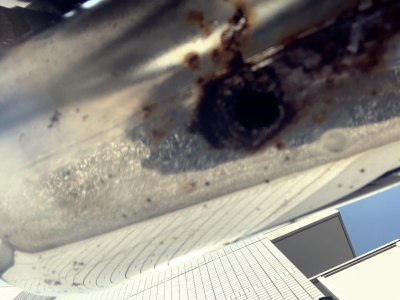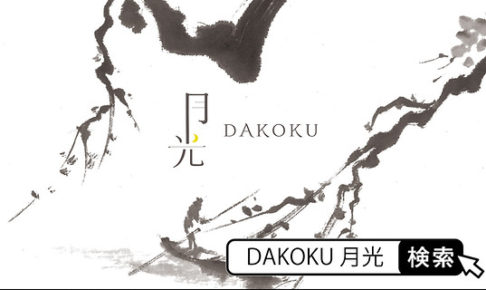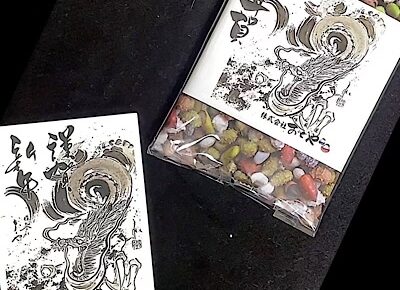はじめまして。
水墨画アーティストの八束徹です。
これから紹介する
5つのテクニックを使うことで、
水墨画を描けるようになります。
ただ墨で描いていただけの白黒の絵を
「水墨画」にしてくれる大切な技法です。
この記事では、その5つの技法、
潤筆、乾筆、ぼかし、かすれ、たらしこみ
についてサクッと話していきます。
目次
水墨画を彩る5つのテクニック
①潤筆(じゅんぴつ)

筆に充分に墨を含ませて、
冴えのある鮮やかな面や線を描きます。
②渇筆(かっぴつ)
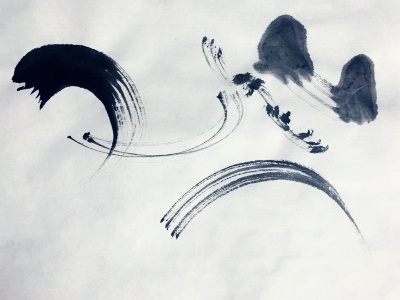
筆に含む墨の量を減らし、かすれを出します。
墨の量や描き方によって様々な変化を楽しめます。
③にじみ

和紙に霧吹きや刷毛などで水を張り、
その上に墨をにじませていくもの。
きれいな水を張るだけでなく、
薄墨で描いたものが乾く前に、
その上に濃墨を滲ませて描く場合もあります。
これは破墨法と呼ばれる技です。
(下記のたらしこみと似ていますが、
たらしこみは「水がにじまない紙」を使い
行う技法です)
④ぼかし

和紙に水を張り、にじみとは逆に、
軽く筆を払いながら墨を広げていき、
遠くにぼやけて見えるような絵を描きます。
遠景に使いがちな技法ですが、
必ずしもそれだけに使う技法
というわけではありません。
⑤たらしこみ

水を張ったり、薄墨で描いたところへ、
その水や薄墨が乾く前に墨を
(薄墨の場合は濃墨)
「たらしこみ」ます。
にじみと似ていますが、こちらの場合は、
水を吸いにくい紙
(鳥の子紙、他、にじみ止めされたものなど)
を使う技です。
道具(筆)ももちろん使いますが、
紙のしわに沿って勝手に流れたり、
自分で紙を動かしてみたり、
そうやってできる模様を
そのまま活かしたりもします。
技名について

歴史が長いせいか、水墨画は
同じ技名でもそれぞれ解釈が違っていて
どれが正解かわからなかったりします。
なのでしっかり技の名前に紐付けて
覚えるというより、
この描き方では墨がどんな動きをして、
絵にどんな効果をもたらすのか。
それを学び、
作画に応用していくことのほうを
優先してください。
*技法については
以下の記事も合わせてご覧ください。
▶︎【必修】水墨画の基本|水墨画を描くための3つの墨の作り方と6つの筆の作り方
まとめ

今回話したのは、
- 必須の5つの技法
- 技名について
です。
これらの技はすべて、
描き手の思い通りにはなりません。
水墨画はその墨や筆に対して、
こういう絵を描きたいからこう動け
こう動かしてやる
とコントロールするものではありません。
目的は墨を支配することでは
決してありません。
自然の流れを活かし、
自由な柔らかい心で、
自分なりの解釈を見つけていきましょう。