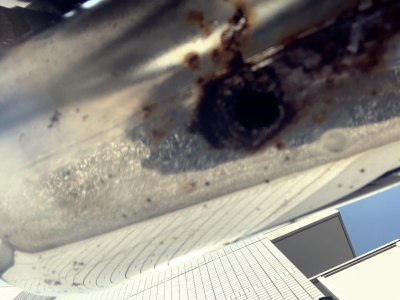こんにちは。
水墨画アーティストの八束徹です。
綿柎開(わたのはなしべひらく)とは、
綿を包む萼(がく)が開くという意味です。
綿の実が開くと、
中から白いふわふわとした
綿(ワタ)の繊維が顔を出します。
これが木綿です。
この木綿が「綿の花」と呼ばれていて、
この七十二候も、
それについて語られています。
この記事では、その綿柎開、
今回描いた水墨画、
について話していきます。
8月23日から8月27日頃の七十二候は、
処暑初候 綿柎開(わたのはなしべひらく)です。
二十四節気は、処暑(しょしょ)に変わります。
その処暑を3つに分けたうちの1番目(初候)です。
目次
綿の実が産む、人を温めるふわふわの「木綿」〜綿柎開(わたのはなしべひらく)
実が開き、生まれてくる綿の花〜木綿

萼(がく)とは、花や実の根元に付いている、
茎と花の間にある葉のようなもので、
これは花を支え守る役割を
担っています。
「柎」の字も同じような意味を持ちます。
この萼が開いて白い綿(木綿)が
生まれるのです。
実際の綿の花は、
七月から八月に咲く夏の花であり、
先にその花が咲いたあとに
綿は実をつけます。
そしてこの時季になるとその実が開き、
製綿の材料となる木綿が
生まれてくるわけです。
その様子を、七十二候において
綿柎開(わたのはなしべひらく)と
名付けているのです。

まるで羊毛のように、
白くふわふわした木綿。
それは加工されて、衣類やタオル、
枕などに使われていきます。
大昔、その栽培方法を知らなかった
ヨーロッパの人々は、
輸入されてくるその木綿が、
羊がなる木から生まれていると
本気で思っていたそうです。
その様子を想像して描かれた絵が
あるくらいです。
ドイツなどではその名残で、
今でも綿のことを
Baumwolle(バオムヴォレ)とよんでいます。
訳すと木のウール。
ウールは羊毛のことですね。
日本国内での綿の生産は
江戸時代に大きく栄え、
そこから生まれた衣類などが、
一般人に定着するようになりました。
そのふっくらとした暖かい性質から、
当時、次の季節の寒さをしのぐためには
とてもありがたいものでした。
暖房器具に頼れる現代では
そのありがたみも薄れがちですが、
当時の人々は、萼(がく)が開いて
綿(わた)が生まれてくる
その様子を見届けながら、
いずれ来る寒い季節への拠り所を
見いだそうとしていたのかも
しれません。
太陽の下で色を変える綿の花〜花

実をつける前に咲く綿の花。
これはまだ木綿の誕生には
少し早い時期の話です。
花の開花時期は七月から八月で、
夏真っ盛りの中で咲きます。
綿の花はクリーム色をしていますが、
それがなんと開花の次の日には
ピンク色に変わります。
まず、開花初日にクリーム色の花が開き、
その日の夕方から夜にかけて
色を変えるのです。
綿の花が色を変える原因は、
夏の暑さと紫外線です。
紫外線をカットした状態で咲いた綿の花は、
翌日もクリーム色のままという
研究結果もあります。
綿の花はその花を咲かせた翌日には、
ピンク色になった状態でしぼみ、
やがて散ってゆきます。
そして、実をつけ、木綿の誕生へとつながっていくのです。
その花の終わりも、
新しい実の誕生もまた、
私達に季節の移り変わりを
見せてくれるのです。
水墨画で七十二候を描く〜綿柎開(わたのはなしべひらく

これは、濃墨で萼から描き始めて、
中墨で葉っぱ、濃墨で枝、葉脈、
そして薄墨で、木綿を描いています。
こういう絵の場合は、枝がクロスしたり、
葉が重なったりも気にしながら描くと
奥行きが出ます。
日本の綿の生産は、
明治時代以降になると
そのほとんどを輸入に頼るようになり、
ほぼ皆無となってしまいました。
そんな綿の栽培ですが、
現在、宮城県では東日本大震災の
復興プロジェクトの一環として、
その栽培が復活しています。
田畑を失った地元農家への
救済策として。
人の心を温め直すために、
木綿が再び活躍しているのです。
私のこの絵も、
何かの役に立てたいです。
まとめ

今回話したのは、
- 七十二候・綿柎開
- 水墨画で描いた綿柎開(わたのはなしべひらく)
についてでした。
次の七十二候は、
処暑次候 天地始粛(てんちはじめてさむし)です。