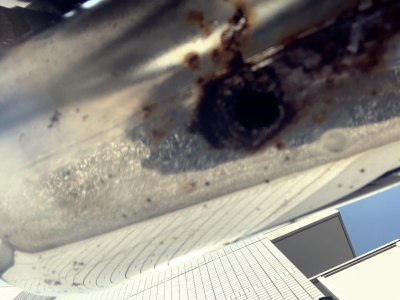緋色の月と、彼女の話。
その夜、彼女が小さい窓から見上げた月は、
暗闇に緋く浮かんでいました。
その月明かりが照らす白いベッドの上には、
彼女が大切に読んでいた一冊の本。
いつかそのベッドから出ていける日を夢見ながら、
心の支えにしていた、ひとり旅の少年の物語。
この歌は、そんな少女を主人公に書いたものでした。
このひとりぼっちの女の子は、
ずっと病に伏して病院のベッドにいます。
そして、時々訪ねてくる誰かさんに、
本の中で覚えたことを話して聞かせています。
何度も何度も読んだ小説です。
知らない遠い世界、
「私以外の人」はきっと
みんな知っているはずの世界。
本を読んで覚えたことを、
自分で経験してきたことのように
少し大人ぶって、彼女は話しました。
そして、小説を何度も読んだ彼女は
とっくに知っていました。
その少年が「何処か」へたどり着くことがないことを。
その旅は延々と続いていくことを。
それが悲しいのか
それが寂しいのか
それが虚しいのか
その少年は月明かりの美しい夜に、
屋根に登り、
痛みをまぎらわすかのように
陽気に踊るのでした。
その姿は道しるべのようでした。
彼女はそんな少年に手を差しのべます。
入っておいでとドアを開けます。
私もひとりぼっちだよ、と。
一緒だよと。
少年は微笑んで、
いたずらっ子のように一度だけ
彼女に手を伸ばして、
彼女がそれを掴む前に引っ込めました。
ありがとう。
それ以上のものは必要ないよ
そう言い残して少年は
屋根をつたって消えていきました。
そして、彼女は目を覚まして
現実に戻りました。
現実を知りました。
もしかしたら、彼女が誰かさんに話していたことは、
本の中で覚えたことではなくて、
本当に彼女がその目で
見てきたことかもしれません。
どこにいても、
そこが病院のベッドの上でも、
目に映ってしまうものについて
話していただけかもしれません。
その夜、彼女が小さい窓から見上げた月は、
暗闇に緋く浮かんでいました。
時は経つとその白いベッドの上から、
彼女の姿はなくなりました。
という物語。
緋い月のワルツ 毎晩サイレンを聴きながら 彼女は眠ってる 病院の冷たいベッドに安心感なんてない 彼が来てそばにいてくれるから 落ち着いていられるだけ 誰かが求人誌を広げて 彼女に見せてる うまく当てはまろうと必死になっている だけど誘いには乗らないんだよ 彼女は夜空を見ているから ほら屋根の上でステップを踏んでいるよ 泣き出しそうな 緋い月のワルツ 寄り添うのが下手な男にはやり方がある それなりのことをしないと誰も守ってくれないよ 彼女はカーテンを閉め切って 誰かの耳元で囁いてる 僕は綱渡りでここへやって来た 彼女に袖を掴まれてここで眠った ピアノの音が聞こえてきたら ねえそっと耳をすましてごらん ほら屋根の上でステップを踏んでいるよ 泣き出しそうな緋い月のワルツ 読みかけの小説と一緒にベッドに潜り込む 他人の話がいつも 人を助けるんだ あの少年はたどり着いたの あの夢降る丘へ 古い傷は今だって蘇るから 旅はいつまで経っても終わらないんだ なんとか少年を助けたくて彼女は ドアを開けて招いたけれど ほら屋根の上でステップを踏んでいるよ 泣き出しそうな緋い月のワルツ ほら屋根の上でステップを踏んでいるよ 高く高く昇る緋い月のワルツ